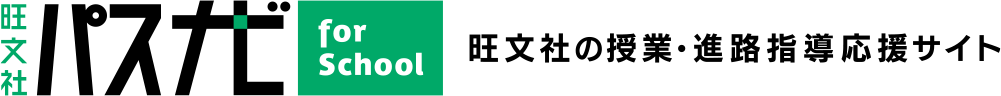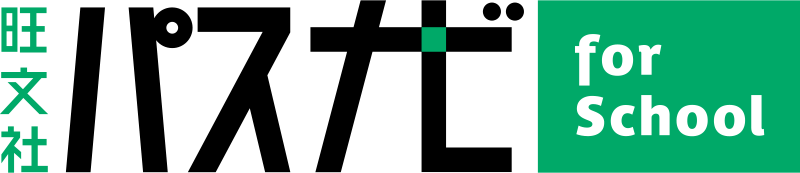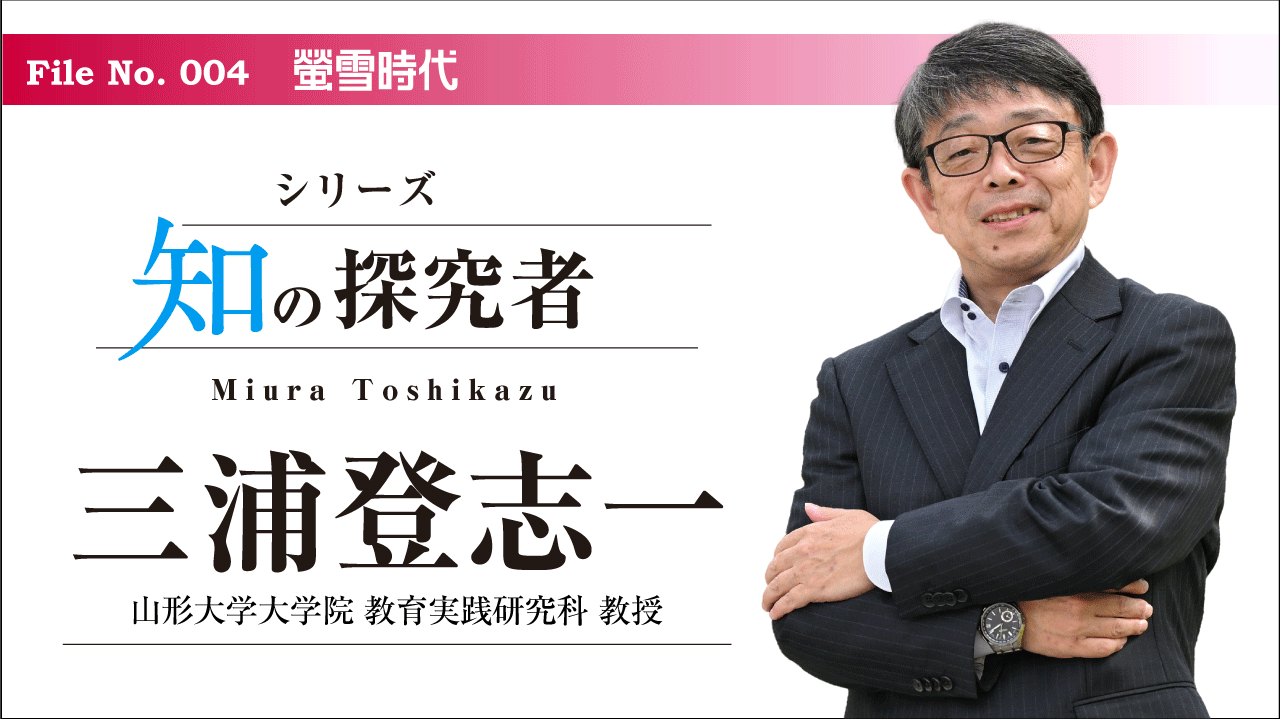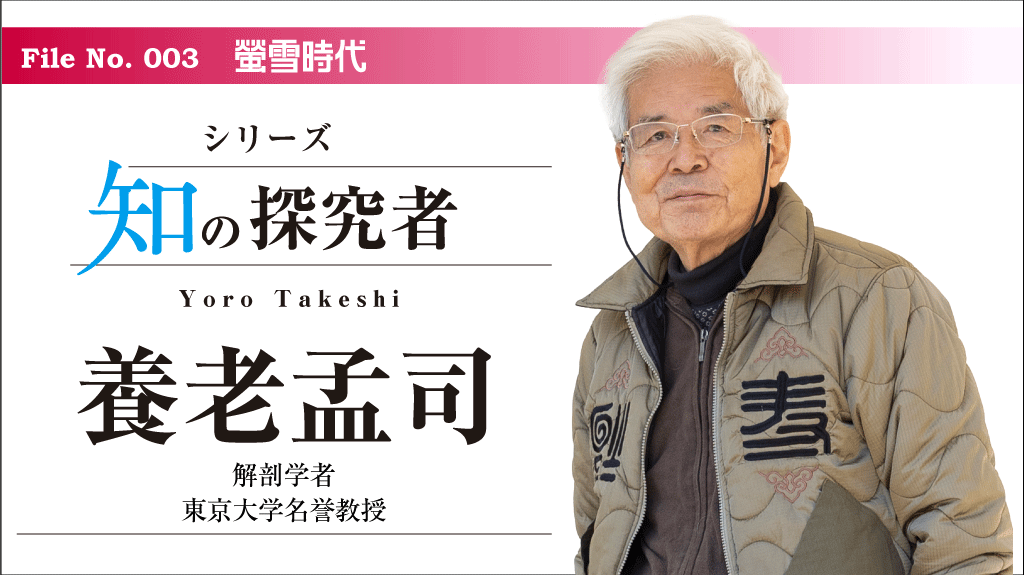
シリーズ 知の探究者/No. 003 養老孟司先生(前編) 「学び」とは、自分が変わりながら身につけていくもの
更新日: 2025/11/6
公開日: 2025/11/6
『螢雪時代』 2024年7月号より掲載
『螢雪時代』で好評連載中の超一流の先生方へのインタビュー記事、「シリーズ知の探究者」が「パスナビ for School」に登場。
「学び」とは何か? を先生方に改めて問いかけ、受験勉強で見失いがちな「学ぶ」という行為を、本質的に考え直す機会を提示しています。第三回目の掲載は、『バカの壁』など、多くの著書で現代社会に警鐘を鳴らす養老孟司先生(解剖学者/東京大学名誉教授)が登場。いまの教育が抱える問題を語っていただきました。
→養老孟司先生のインタビュー全記事は『螢雪時代』2024年7月号に掲載されました。全文を読みたい方はこちら

本当の財産は、
学ぶことができるものだけ

大の虫好きでも知られ、自然とヒトとの関わりについても思索を重ねている養老孟司先生。自身の昆虫標本を収蔵する「養老山荘」でお話をお聞きしました。
編集協力:(有)サード・アイ 取材:金丸敦子 写真:石原秀樹
――「学び」とは何でしょうか。
養老 「学び」とは「身につけるもの」だと思います。「知る」ことで、目からウロコが落ち、ものの見方が変わり、自分が変わっていく。それをくりかえしていくことで、「学び」が身についていく。それが学ぶということでしょう。
「学び」というのは頭の中の知識を増やしていくことではありません。身体も頭と同時に体験し、訓練することによって、知識を「身につく」ものにするのが「学び」です。知識だけ増やしても、それが行動に結びつき、応用できなければ意味がない。「学び」が「身につく」ことで臨機応変に対応できるのです。