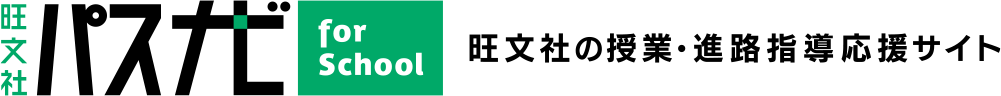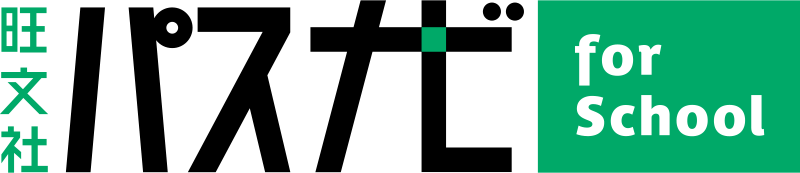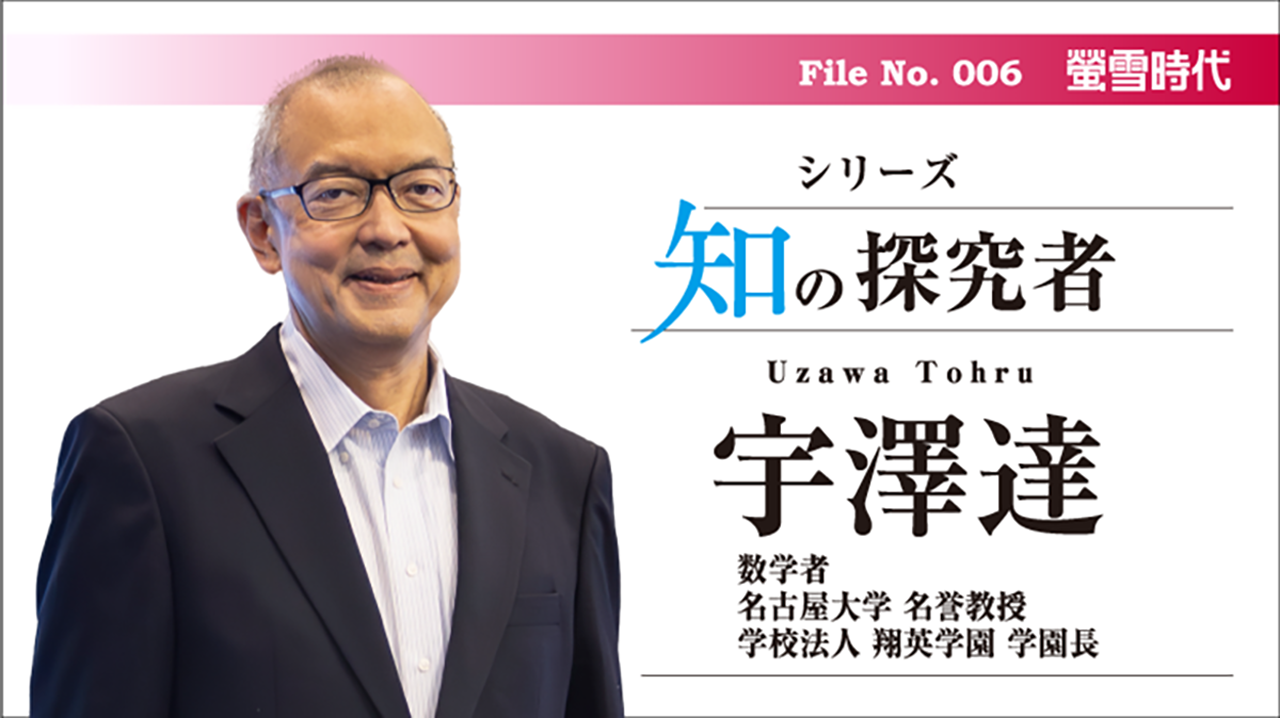『螢雪時代』 2025年9月号より掲載
<前編から続く> 『螢雪時代』で好評連載中の超一流の先生方へのインタビュー記事、『シリーズ「知の探究者」』。
「学び」とは何か? を先生方に改めて問いかけ、受験勉強で見失いがちな「学ぶ」という行為を、本質的に考え直す機会を提示していきます。今回は『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』などのベストセラーで話題の、今井むつみ先生(慶應義塾大学名誉教授)の後編です。
今後は鷲田清一先生(哲学者/大阪大学・京都市立芸術大学名誉教授)、養老孟司先生(解剖学者/東京大学名誉教授)など、日本の賢人たちが続々登場予定です。ぜひご期待ください。

「知識の断片」を五感と結びつけて
「活きた知識」にするのが大切

認知心理学や言語心理学、発達心理学を専門とし、一般向けの著書も多数刊行している今井むつみ先生に、「学び」について認知科学の視点からお話を伺いました。
編集協力:(有)サード・アイ 取材:金丸敦子 写真:石原秀樹
前回からの続き
今井 だから、他のウサギに使えるためには、ウサギを抽象化して、「ウサギってどういうものか」「どういうものに“ウサギ”ということばを使えるのか」という、その範囲を考えなければいけない。たとえば、目の前のウサギが白くて耳の長いウサギだった時に、茶色いものはウサギなのか、すごく小さいものもウサギでいいのか、耳がもっと短くてもいいのか。そういうある種の概念を持たないと、「ウサギ」ってことばは使えないわけですよね。では、どうすれば目の前の白くて耳の長いウサギとは違う、耳の短いウサギや、茶色いウサギを見ても「ウサギ」ということばが使えるようになるのでしょうか。それは実際に見て、触って、においを嗅ぐなど、五感と結びつける経験をし、「ウサギとはこういうものだ」と自分で発見しているからなのです。これを抽象化、あるいは一般化の過程と言います。
親から1つの「点」としてのウサギの事例を教えてもらい、「ここに注目すればいい」ということに自分で気づいて暗黙の知識として蓄え、「点」を「面」にしていく。こうして蓄えた暗黙の知識を「スキーマ」と言います。人はこの「スキーマ」を使って、新しいことばをどんどん覚えていくんです。ですから、「スキーマ」ができる前と後では、ことばを覚えるスピードが全然違ってきます。